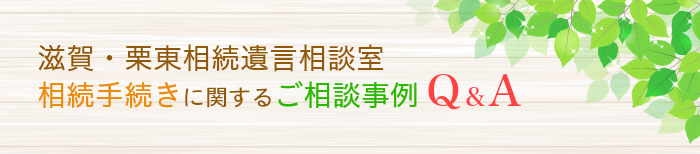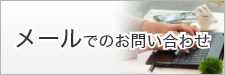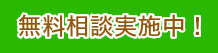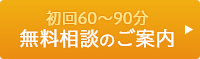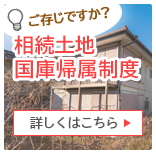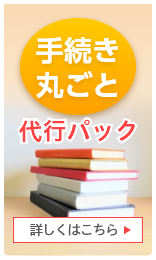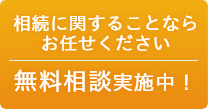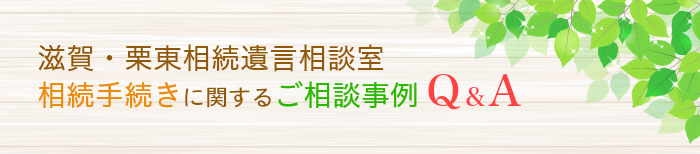
遺言書の作成
2024年02月05日
Q:父の遺言書を確認したところ、私が遺言執行者となっていました。行政書士の先生、私が遺言執行者としてやるべきことはなんですか?(湖南)
こんにちは、私は湖南在住の50代男性です。
この度、同じく湖南に住んでいた父が闘病の末に亡くなりました。父は病気を患っていたこともあり、早いうちから公正証書遺言を用意していました。なお、相続人は母と私と妹の3人のようです。
先日、妹と一緒に公証役場に行き、公正証書遺言の内容を確認すると、「長男〇〇が遺言執行者である」と文末に記載されていました。生前に父から公正証書遺言があることは聞いていましたが、遺言執行者に関しては何も話をされなかったので、この事態を受け今後どのようにすべきか悩んでおります。
私の職場も湖南にあるため、役所や金融機関などは行きやすい距離ではあるものの、これから仕事が繁忙期に入るため日中に時間を取ることが難しく、遺言執行者として役目を果たせるのか不安です。行政書士の先生、遺言執行者として私がやるべきことは何でしょうか?(湖南)
A:遺言書に記載されている内容を実現するために、手続きを行う人のことを「遺言執行者」と言います。
滋賀・栗東相続遺言相談室にご相談いただき、誠にありがとうございます。
遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言をスムーズに執行するために相続財産の管理や諸々の手続きを行う者のことです。遺言書で遺言執行者に任命された者は、責任をもって遺言の実現のため、相続財産の管理(各種名義変更など)や遺言書の内容に沿って手続きを進めなければなりません。
しかし、遺言執行者に任命されたからといって必ず就任しなければならないわけではありません。基本的に相続人本人の意思で決めることができるため、遺言執行者になることを承諾しない旨を相続人に連絡すれば辞退することも可能です。なお、就任後(遺言執行者に就任する承諾をした後)であっても、正当な事由があり家庭裁判所の許可を得た場合にのみ、遺言執行者を辞任することができます。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南にお住いの皆様に向けて相続・遺言に関する初回無料相談を実施しております。
今回の湖南のご相談者様のように、「遺言書で遺言執行者に任命されたが、仕事が忙しく対応ができるか不安」「遺言執行者になったので、専門家にサポートをしてほしい」など相続・遺言に関するたくさんのご相談をこれまでにいただいております。
遺言執行者として相続財産の管理や手続きを行うことは、想像以上にやるべきことが多く負担に感じられることもあるでしょう。滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続や遺言の専門家が湖南の皆様に寄り添い、ご状況に合わせて適切で丁寧なサポートをご提案させていただきます。
まずは、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談にお問い合わせください。湖南の皆様のお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。
2023年11月02日
Q:行政書士の先生、両親が連名で遺言書を作成したと話していたのですが、この遺言書は法的に問題ありませんか?(栗東)
栗東に住む両親が作成した遺言書について、行政書士の先生に質問です。
お盆に栗東の実家に帰省した際、相続についての話になりました。父は栗東の実家の他にも栗東に土地を持っているので、相続人となる私や2人の弟が相続について揉めることのないように、遺言書を作成しておいたとのことでした。遺言書の具体的な内容までは聞いていないのですが、父は「夫婦で話し合って、夫婦2人でしっかり署名捺印したから安心するように」と話していたのが気になります。
遺言書は夫婦連名で作成しても問題ないのでしょうか?せっかく作成しても法的効力のない遺言書では意味がないのではないのかと思い、質問させていただきました。(栗東)
A:2人以上の署名がされた遺言書は、たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても法的に無効となります。
民法では「共同遺言の禁止」といって、2名以上の者が共同して一つの遺言書を作成することを禁じています。たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても同様ですので、残念ながら栗東のご両親が作成された遺言書は法的に無効となってしまいます。
遺言書は、遺言者(遺言を残す人)の自由な意思を反映して作成するものです。複数名で遺言書を残そうとすると、一部の人間が主導的な立場で作成してしまい、その他の者の自由な意思が反映されていないのではないかという疑いが生じます。
さらに、連名で作成した場合は遺言書の撤回の自由も奪われてしまいます。本来遺言書は遺言者が自由に撤回できるものですが、連名で作成してしまうと、1人の意思では遺言書が撤回できず、共同作成者全員の同意を得なければならなくなってしまいます。このような理由から、遺言書を連名で作成することは認められていないのです。
遺言書は、亡くなった方の最後の意思が書かれた大切な書面です。第三者の介入によって制約がかかり自由が奪われてしまうようでは遺言書とはいえません。それゆえ、遺言書の形式は法律で明確に定められており、定められた形式に従って作成されていない遺言書は法的に無効となってしまいます。
栗東に暮らすお父様は遺されたご家族のことを思って遺言書を作成されたとのことですので、遺言書を法的効力のあるものにするためにも、遺言書作成に精通したプロに一度相談されるようお伝えになってはいかがでしょうか。
滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書の作成サポートも承っております。初回無料相談にて、栗東の皆様の遺言書作成に至った思いをお伺いしたうえで、どのような形で遺言書を作成すべきかアドバイスさせていただきます。遺言書作成だけでなく、相続全般についても滋賀・栗東相続遺言相談室へお任せください。栗東の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2023年08月02日
Q:直筆で書かれた遺言書を発見したのですが、どうすれば良いでしょうか?行政書士の先生に伺いたいです。(栗東)
先日、栗東で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀を終え、遺品の整理をしに栗東の実家に行ったところ、遺言書を発見しました。封筒の表面に書かれている文字からして、父が直筆で書いた遺言書かと思います。中身を確認するのは、姉や弟など相続人にあたる親族が集まってからにしようと思っていますが、遺言書は今すぐに開けた方が良いのでしょうか。遺言書を発見した場合、何か手続きが必要なのでしょうか。どうすればいいか分からず困っているため、どのように進めるか教えていただきたいです。(栗東)
A:自筆で書かれた遺言書は勝手に開けずに、家庭裁判所で検認を行ってください。
相続で遺言書が発見された場合は、基本的に法律で定められた内容よりも遺言書に書かれている内容が優先されます。ご相談者様が発見された遺言書は自筆証書遺言という手書きで書かれた遺言書になるかと思います。自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。検認の手続きをせずに開封してしまった場合、罰則として5万円以下の過料が科されてしまいますので、注意しましょう。
自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所にて検認の手続きが必要になります。検認手続きには、戸籍謄本等の書類を家庭裁判所に提出します。検認の手続きを行うことで、遺言書の形状や訂正等、検認日に確認された内容を明確にすることができます。また、遺言書の存在と内容を相続人が確認することができ、偽造防止にも効果的です。
なお、2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになりました。もしも法務局で保管していた場合は、家庭裁判所での検認は不要です。
遺言書の検認手続きが済んだら、検認済み証明書が付いた遺言書の内容を元に手続きを進めましょう。申立人以外の相続人がいない状態であっても検認の手続きは行うことはできますが、検認を行わなければ遺言書の内容に沿った各種手続きを進めることができません。もしも、遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害する内容が書かれていた場合、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。
滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書についてのご相談を受け付けております。栗東近郊にお住いの皆様のサポートをしており、初回は無料でご相談いただけます。遺言書の作成から相続のお手続きまで専門家がサポートしておりますので、安心してお任せください。栗東の皆様のお問合せをお待ちしております。
まずはお気軽にお電話ください
0120-172-690
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応